スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
「自己肯定感」って大事なの?!
2022年06月22日
元気ですか?!精神的に。
今回は「自己肯定感」を考えてみようの巻です♬
そもそも「自己肯定感」って何?そんなに大事なの?
「自己肯定感」が低いとか、上げようとか言われるけど、余計なお世話です。ていうかどうやったら上がるの??
アドラー心理学的にはあらゆる悩みは「対人関係」の悩みと言われています。

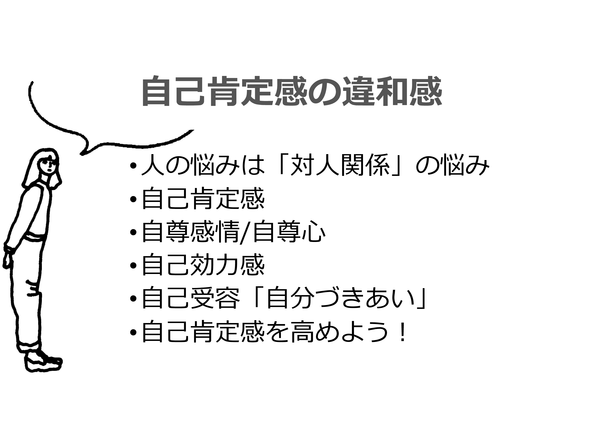





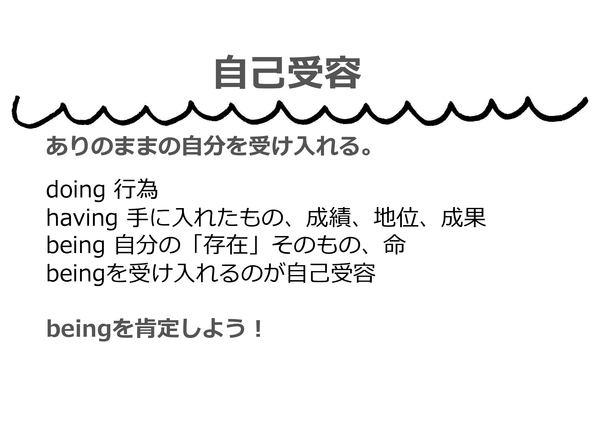

「対人関係」のベースになっているのは、実は「自分自身」との関係性。つまり、「自分付き合い」が上手か否かが「他人付き合い」にも影響しているのです。
自分と上手に付き合うために。
参考にしてね♬
今回は「自己肯定感」を考えてみようの巻です♬
そもそも「自己肯定感」って何?そんなに大事なの?
「自己肯定感」が低いとか、上げようとか言われるけど、余計なお世話です。ていうかどうやったら上がるの??
アドラー心理学的にはあらゆる悩みは「対人関係」の悩みと言われています。

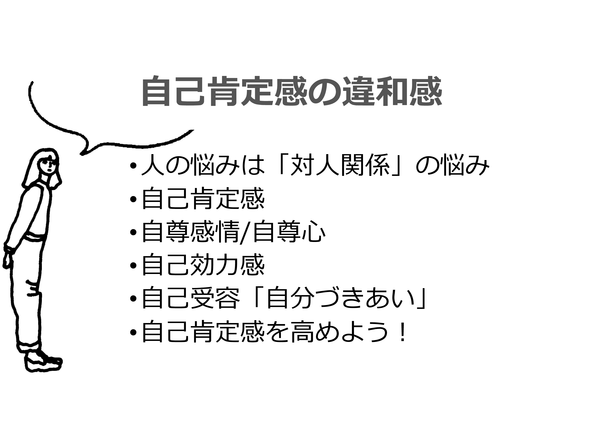





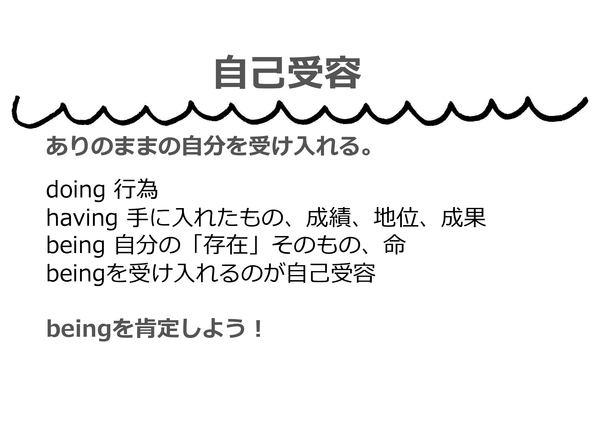

「対人関係」のベースになっているのは、実は「自分自身」との関係性。つまり、「自分付き合い」が上手か否かが「他人付き合い」にも影響しているのです。
自分と上手に付き合うために。
参考にしてね♬
孤立を考える 精神科医がこっそり教える素晴らしき「社会的処方」の世界
2022年06月16日
元気ですか!?精神的に。
今回は『孤立を考える 精神科医がこっそり教える素晴らしき「社会的処方」の世界』です♬
「孤立」は大きな社会問題で、日本の高齢者のうち30%がつながりがないという報告があります。
これは世界的な問題で、イギリスでは「社会的孤立」が経済に与える影響は年間5兆円と言われ、「孤立担当大臣」なる役職があるほどです。
実はこの「孤立担当大臣」日本にもいるのです。知ってました?
この世界的な課題を解決すべく注目を集めているのが、「社会的処方」♬
「孤立」という病を地域のつながりで治す方法なんです♬
「処方」というと「薬」をイメージしますが、「薬」ではなく社会との「つながり」を提供する「社会的処方」
担い手を「リンクワーカー」「ケアナビゲーター」と言いますが、誰にでも出来て、どことつないでもいいステキな概念なのです♬

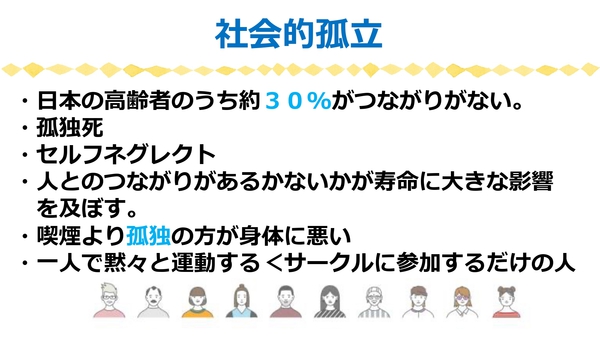






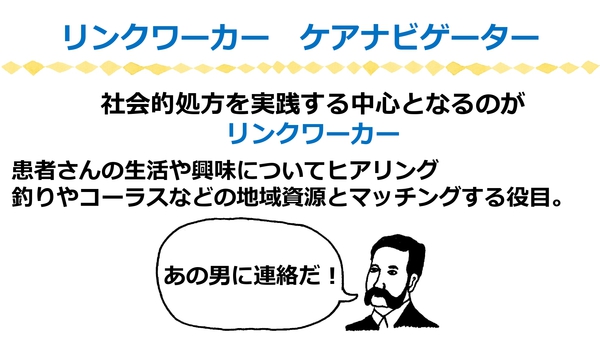


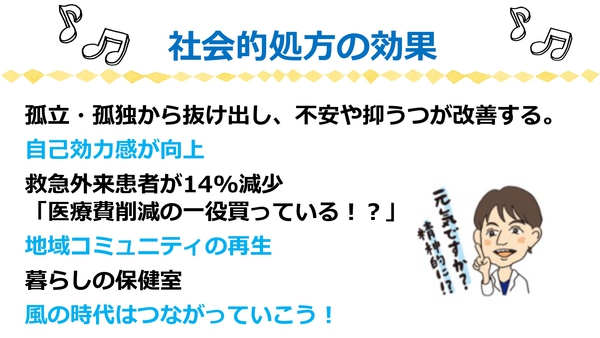
風の時代の価値観にマッチする「社会的処方」の世界♬
参考にしてね♬
今回は『孤立を考える 精神科医がこっそり教える素晴らしき「社会的処方」の世界』です♬
「孤立」は大きな社会問題で、日本の高齢者のうち30%がつながりがないという報告があります。
これは世界的な問題で、イギリスでは「社会的孤立」が経済に与える影響は年間5兆円と言われ、「孤立担当大臣」なる役職があるほどです。
実はこの「孤立担当大臣」日本にもいるのです。知ってました?
この世界的な課題を解決すべく注目を集めているのが、「社会的処方」♬
「孤立」という病を地域のつながりで治す方法なんです♬
「処方」というと「薬」をイメージしますが、「薬」ではなく社会との「つながり」を提供する「社会的処方」
担い手を「リンクワーカー」「ケアナビゲーター」と言いますが、誰にでも出来て、どことつないでもいいステキな概念なのです♬

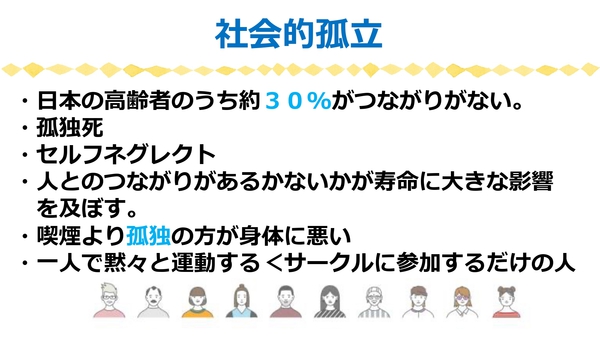






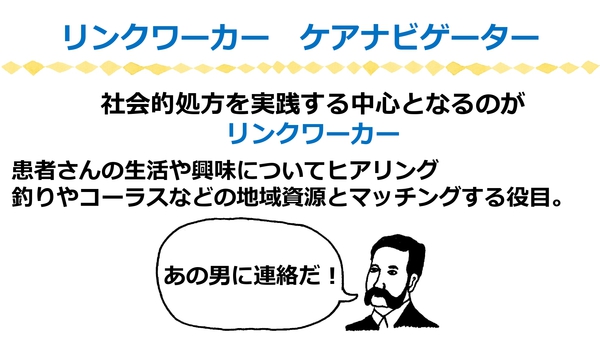


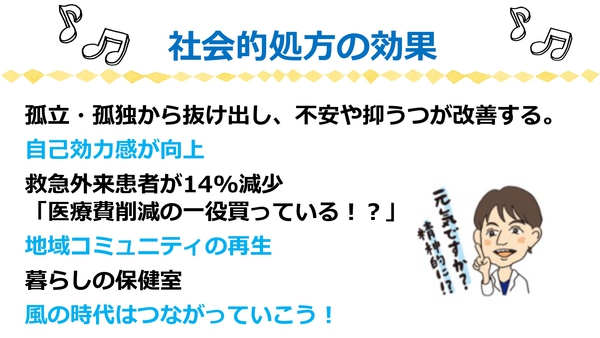
風の時代の価値観にマッチする「社会的処方」の世界♬
参考にしてね♬
人はなぜ心を病むのか?〜心の時代の対処法〜
2022年06月10日
元気ですか?!精神的に。
今回は「人はなぜ心を病むのか?〜心の時代の対処法〜」です♬
心の時代なのに、かえって心を病んでしまう…その矛盾を人類の歴史から紐解きます。
「心」の概念っていつからあるの?
そもそも「心」ってどこにあるの?
「心」の語源は「内臓」で、ヘブライ語では「子宮」と言われています。
つまり「心」はもともと「子宮」にあったのです♬(甲骨文字より)
そこから時代とともに「肝(内臓)」→「横隔膜」→「心臓」→「脳」と変遷します。
あれ?!上へ上へと昇っているのではっ!?
そう、怒りの表現も、腹が立つ→ムカつく→頭にくると昇ってきています。
いよいよ昇り切り、脳が肥大化して疲れてしまったのが「心の時代」というわけです。


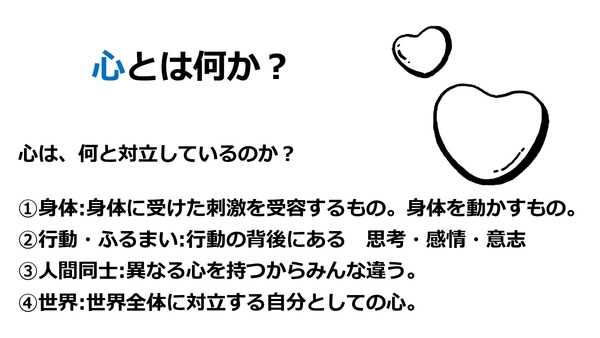






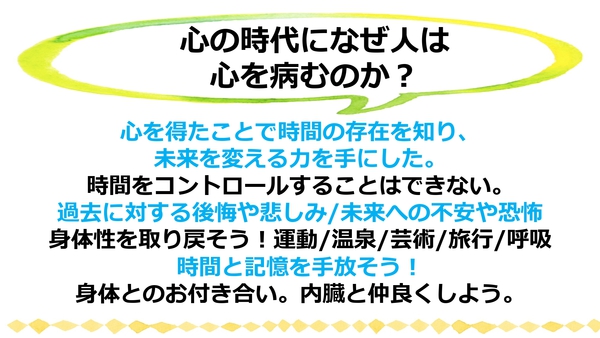
というわけで、心を癒すポイントはむしろ「身体性」を取り戻すこと♬
マインドフルネスが良いと言われる理由がここにあるのです♬
参考にしてね♬
今回は「人はなぜ心を病むのか?〜心の時代の対処法〜」です♬
心の時代なのに、かえって心を病んでしまう…その矛盾を人類の歴史から紐解きます。
「心」の概念っていつからあるの?
そもそも「心」ってどこにあるの?
「心」の語源は「内臓」で、ヘブライ語では「子宮」と言われています。
つまり「心」はもともと「子宮」にあったのです♬(甲骨文字より)
そこから時代とともに「肝(内臓)」→「横隔膜」→「心臓」→「脳」と変遷します。
あれ?!上へ上へと昇っているのではっ!?
そう、怒りの表現も、腹が立つ→ムカつく→頭にくると昇ってきています。
いよいよ昇り切り、脳が肥大化して疲れてしまったのが「心の時代」というわけです。


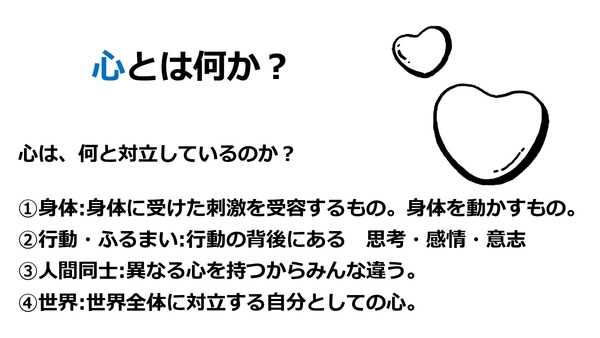






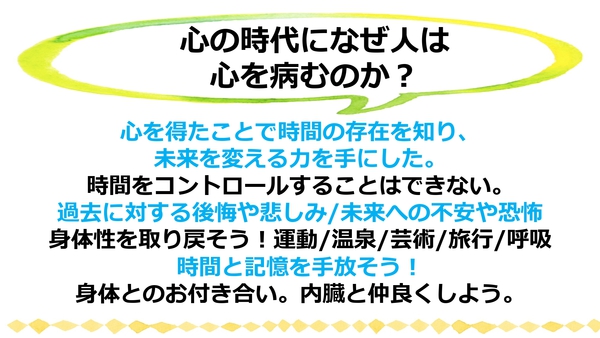
というわけで、心を癒すポイントはむしろ「身体性」を取り戻すこと♬
マインドフルネスが良いと言われる理由がここにあるのです♬
参考にしてね♬
「ふつう」とは何か?!ASDの「生きづらさ」「生きにくさ」から考える「ふつう」の世界♬
2022年05月27日
元気ですか?!精神的に。
飛騨高山の精神科医益田大輔です♬
今回は「ふつう」とは何か?!ASD (自閉症スペクトラム障害)の「生きづらさ」「生きにくさ」から考える「ふつう」の世界です♬
精神状態が正常か異常か判断する物差しは「ふつう」か「ふつうじゃないか」の判断です。
とはいえ、「ふつう」って…何?
「ふつうじゃない」って文化や価値観に依るのかも??
この謎をASD (自閉症スペクトラム障害)の特性を踏まえてじっくり考察♬
後半は「生きづらさ」と「生きにくさ」の違いも考えます♬
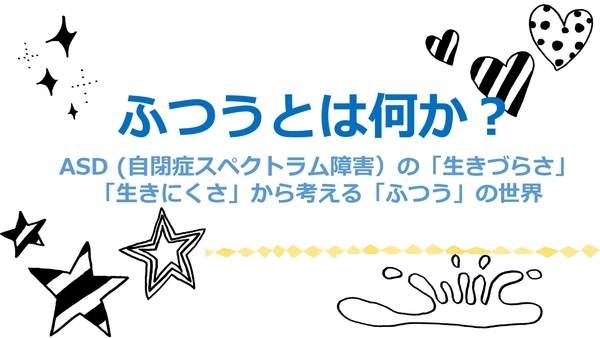


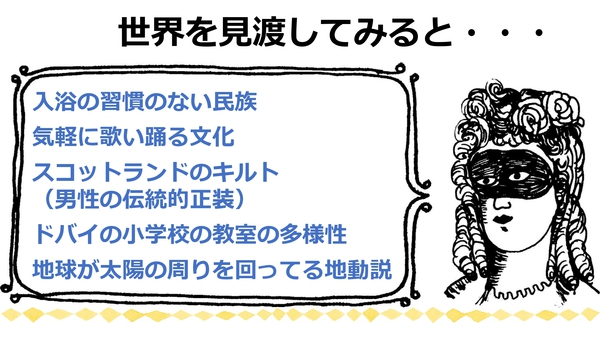






ともあれ、「ふつう」の概念が広がるといいですね♬
寛容な社会が何よりなのです。参考にしてね♬
飛騨高山の精神科医益田大輔です♬
今回は「ふつう」とは何か?!ASD (自閉症スペクトラム障害)の「生きづらさ」「生きにくさ」から考える「ふつう」の世界です♬
精神状態が正常か異常か判断する物差しは「ふつう」か「ふつうじゃないか」の判断です。
とはいえ、「ふつう」って…何?
「ふつうじゃない」って文化や価値観に依るのかも??
この謎をASD (自閉症スペクトラム障害)の特性を踏まえてじっくり考察♬
後半は「生きづらさ」と「生きにくさ」の違いも考えます♬
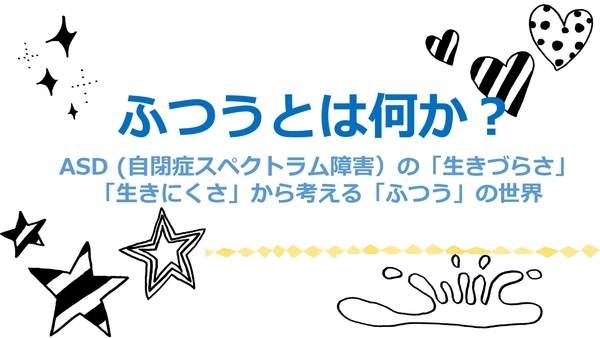


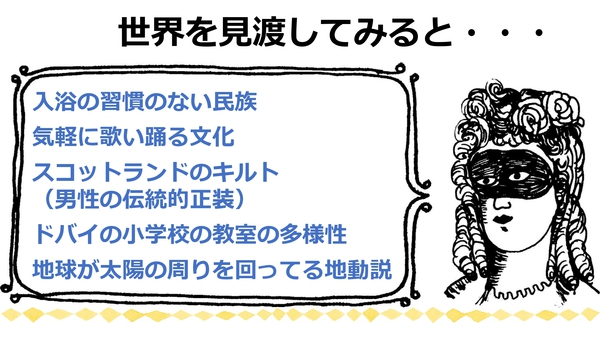






ともあれ、「ふつう」の概念が広がるといいですね♬
寛容な社会が何よりなのです。参考にしてね♬
精神科医がこっそり教える目からウロコ?!精神を健康に保つ9つの秘訣
2022年05月23日
元気ですか?!精神的に。
今回は「精神科医がこっそり教える目からウロコ?!精神を健康に保つ9つの秘訣」です♬
かの精神病理学の巨匠、中井久夫先生の「精神健康の基準」に基づき、9つの秘訣をご紹介♬
「病」や「反応」はある意味「成長」や「治癒」の過程でもあるのです♬
「退行」(赤ちゃん返り)や「嘘をつく」こと「複数の人格がいる」(多重人格)ことは、一見わるい反応に思えますが、実は子どもの「成長」にとっても必要なことなのです♬

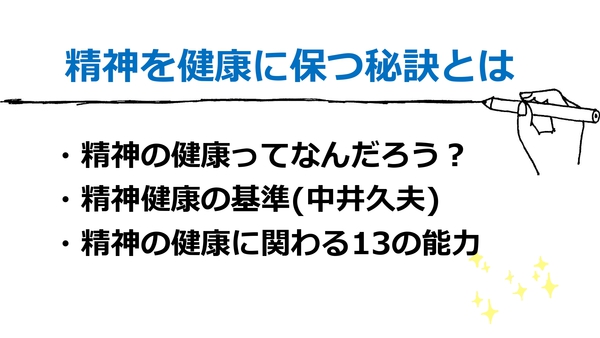
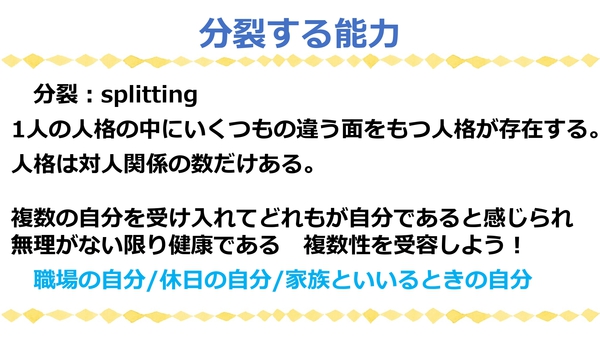
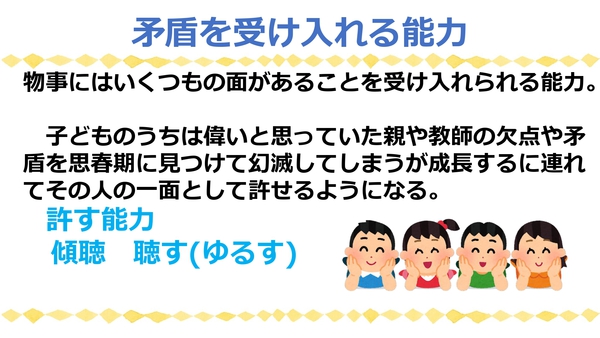
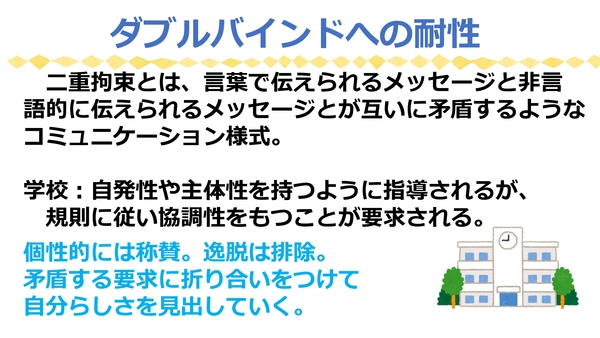
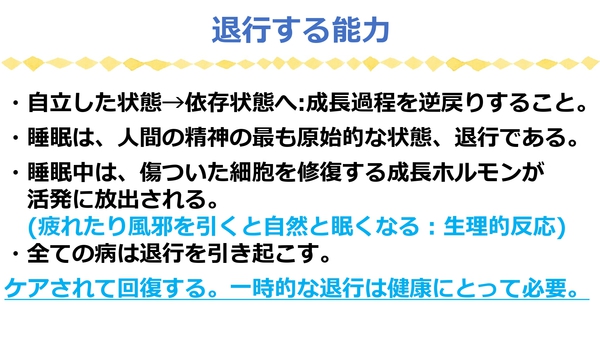

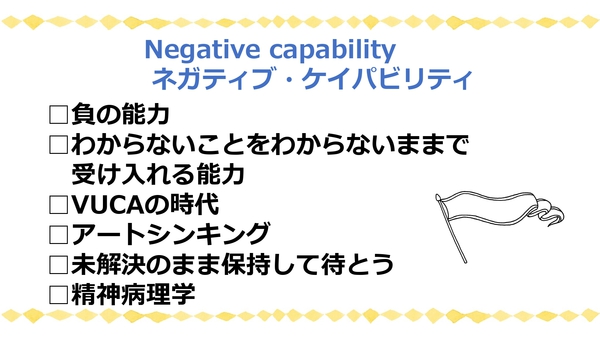


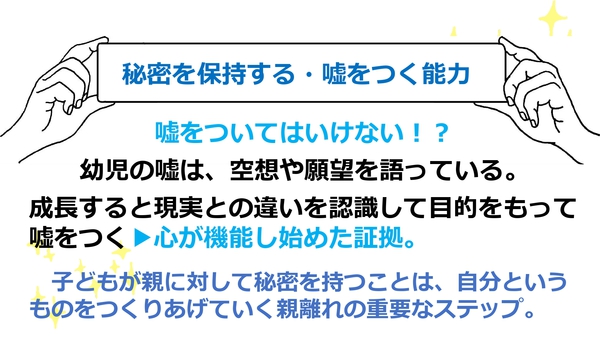


まさに目からウロコ。
是非参考にして下さい♬
今回は「精神科医がこっそり教える目からウロコ?!精神を健康に保つ9つの秘訣」です♬
かの精神病理学の巨匠、中井久夫先生の「精神健康の基準」に基づき、9つの秘訣をご紹介♬
「病」や「反応」はある意味「成長」や「治癒」の過程でもあるのです♬
「退行」(赤ちゃん返り)や「嘘をつく」こと「複数の人格がいる」(多重人格)ことは、一見わるい反応に思えますが、実は子どもの「成長」にとっても必要なことなのです♬

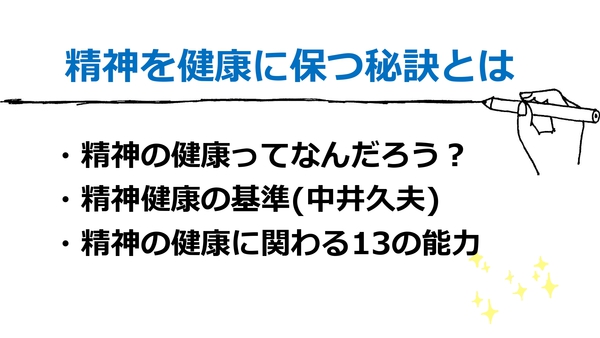
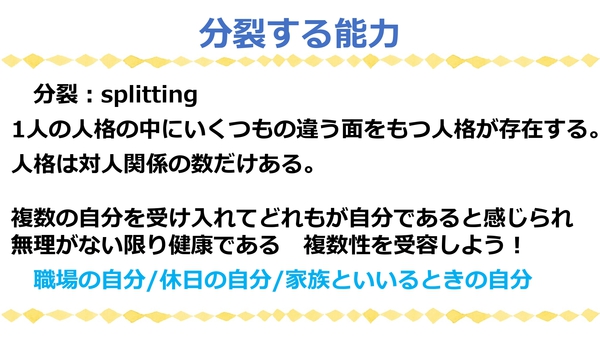
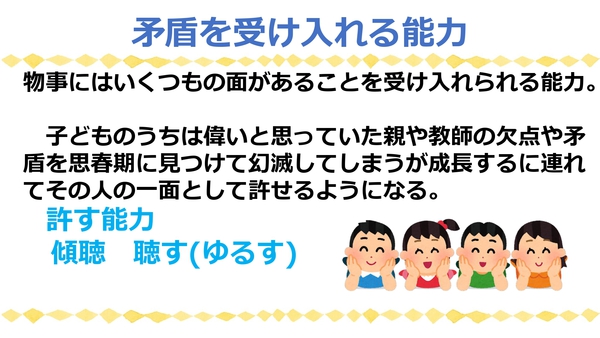
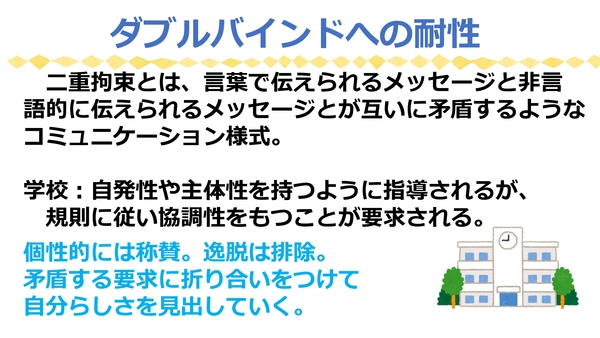
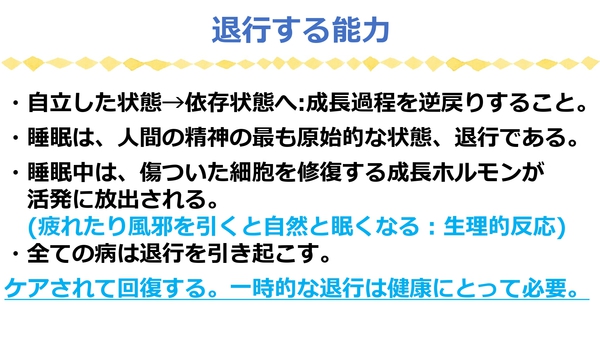

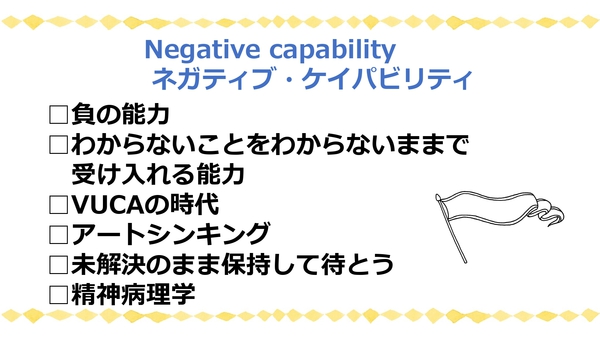


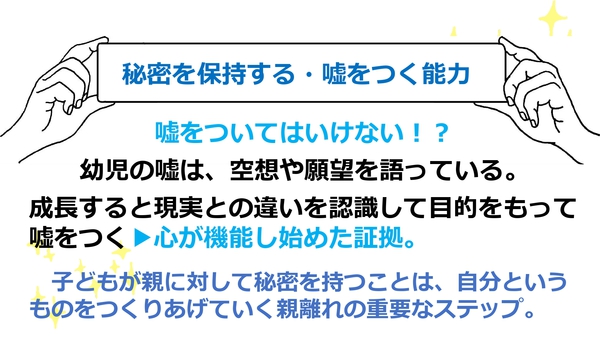


まさに目からウロコ。
是非参考にして下さい♬
『不登校を考える』
2022年05月15日
元気ですか?!精神的に。
飛騨高山の精神科医、益田大輔です。
今回は『不登校』についてのお話しです。
『不登校』は病気ではなく状態ですが、昨今の大きな社会問題でもあり、立場によって見え方も違い、時に感情的にぶつかることも多く、俯瞰的な解釈・知識の共有が必要です。
後半は梨木香歩さんの名著『西の魔女が死んだ』を参考に『不登校』に向き合う姿勢を徹底解説♬
参考になりますよ〜♬






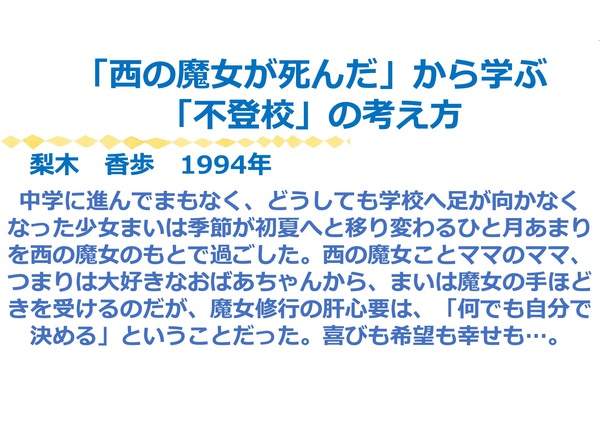


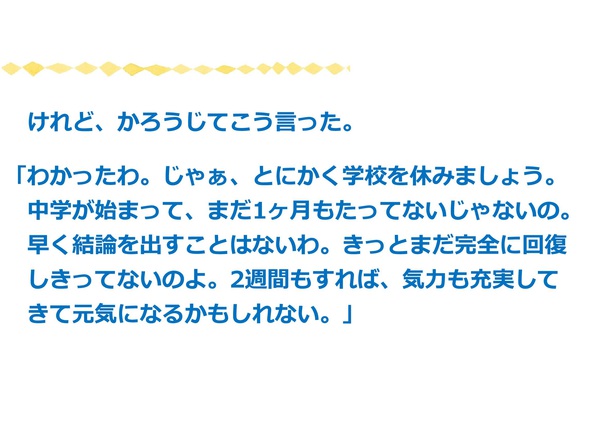

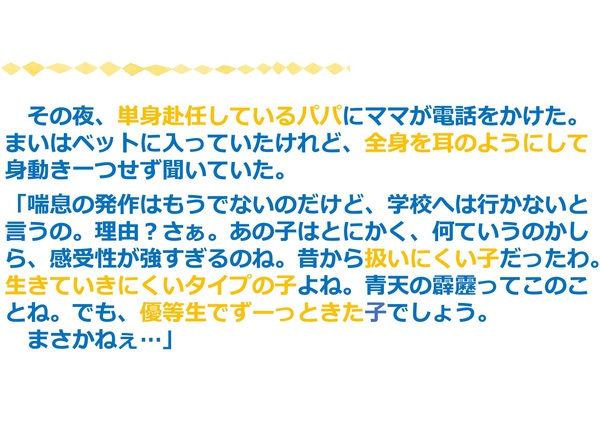


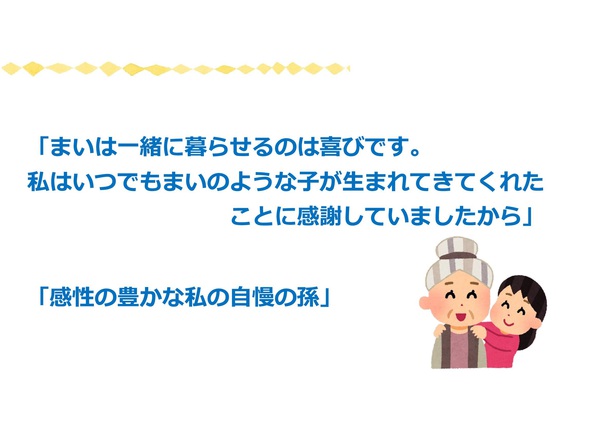

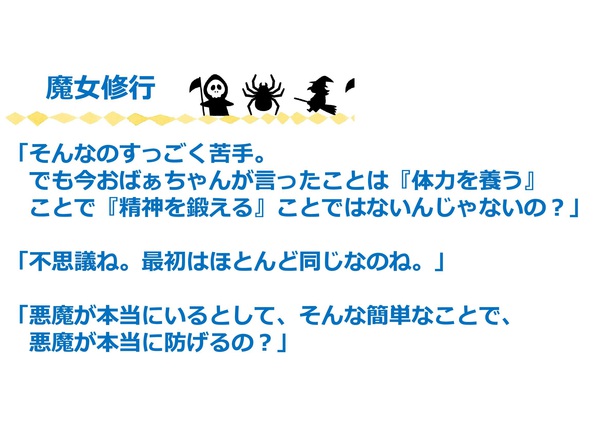


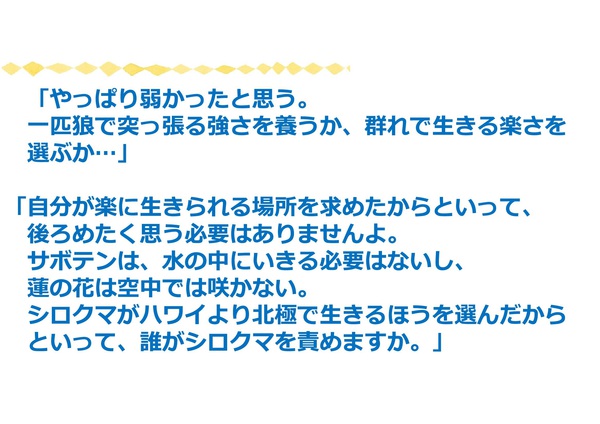


人生100年時代、VUCAの時代、風の時代、あわいの時代など、これから社会構造も価値観も変わっていきますが、教育や学習のあり方も多様化していくのでしょう。
飛騨高山の精神科医、益田大輔です。
今回は『不登校』についてのお話しです。
『不登校』は病気ではなく状態ですが、昨今の大きな社会問題でもあり、立場によって見え方も違い、時に感情的にぶつかることも多く、俯瞰的な解釈・知識の共有が必要です。
後半は梨木香歩さんの名著『西の魔女が死んだ』を参考に『不登校』に向き合う姿勢を徹底解説♬
参考になりますよ〜♬






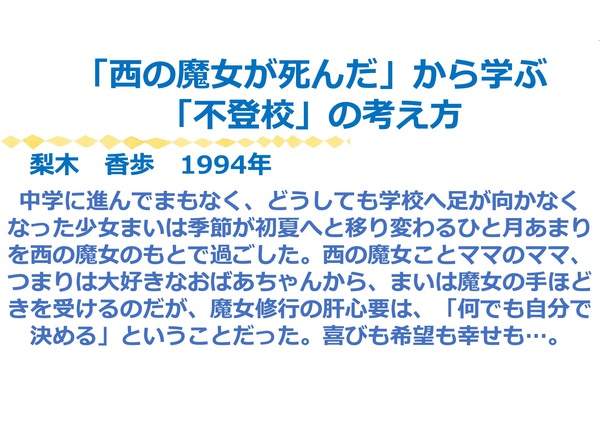


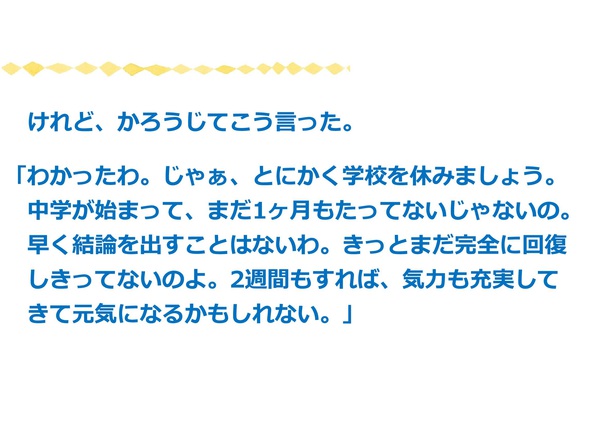

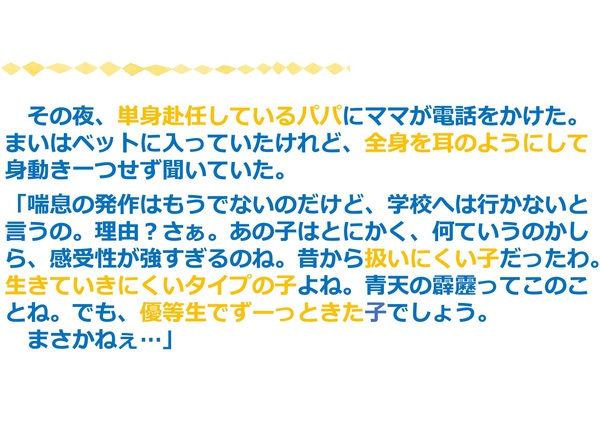


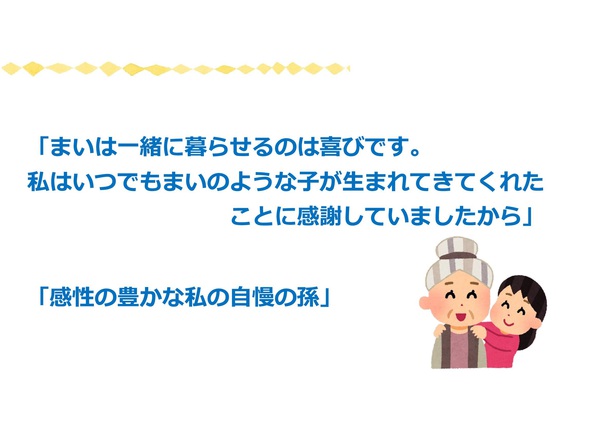

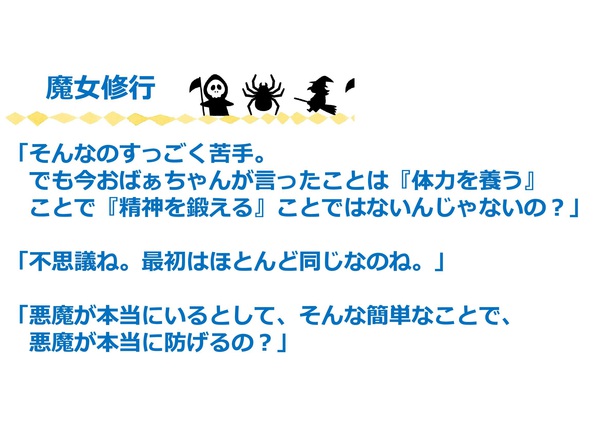


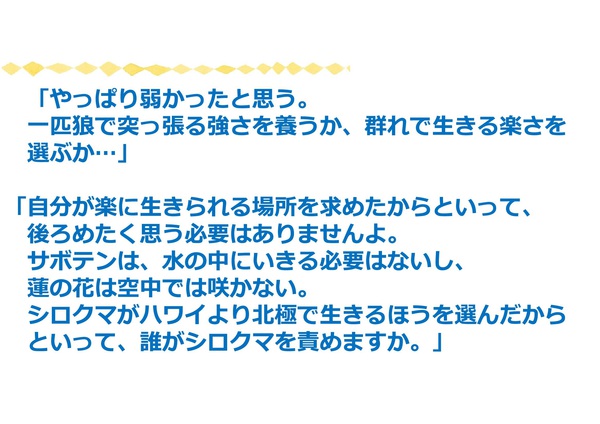


人生100年時代、VUCAの時代、風の時代、あわいの時代など、これから社会構造も価値観も変わっていきますが、教育や学習のあり方も多様化していくのでしょう。
不安の抱きしめ方
2022年03月23日
元気ですか!?精神的に。
今回は「不安」との付き合い方についてのお話です♬
精神的に不調になると、そこには必ず「不安」があります。
つまり、不安をコントロール出来ればこころは随分楽になるわけです。
不安は不安を呼ぶので悪循環に陥りやすく、膨らんだ不安によって人は疲弊していきます。
そんな不安に対する目から鱗の対処法♬
◆00:00
不安の抱きしめ方

◆00:13
大切なのは、不安をなくすことではない
コントロールすること

◆00:33
在外化/脱中心化

◆01:36
名前をつける

◆02:12
不安な時の5つの質問

◆02:56
一回疑おう

◆03:55
会話は、頭を整理し
現実と思いこみの違いを認識
する為の効果的な方法

◆05:16
呼吸

◆05:42
まとめ

『精神科医がこっそり教える不安の抱きしめ方』
是非参考にして下さい♬
今回は「不安」との付き合い方についてのお話です♬
精神的に不調になると、そこには必ず「不安」があります。
つまり、不安をコントロール出来ればこころは随分楽になるわけです。
不安は不安を呼ぶので悪循環に陥りやすく、膨らんだ不安によって人は疲弊していきます。
そんな不安に対する目から鱗の対処法♬
◆00:00
不安の抱きしめ方

◆00:13
大切なのは、不安をなくすことではない
コントロールすること

◆00:33
在外化/脱中心化

◆01:36
名前をつける

◆02:12
不安な時の5つの質問

◆02:56
一回疑おう

◆03:55
会話は、頭を整理し
現実と思いこみの違いを認識
する為の効果的な方法

◆05:16
呼吸

◆05:42
まとめ

『精神科医がこっそり教える不安の抱きしめ方』
是非参考にして下さい♬












